ここ半年くらい睡眠中に何度も夢を見てしまい、朝起きるのもつらくスッキリしない。仕事中も度々眠気が襲って来るようになってしまいました。
このままでは集中力が低下し仕事にも影響してしまいます。なにより憂鬱な気分のままの毎日が辛いです。
睡眠の質が低下し毎日が憂鬱
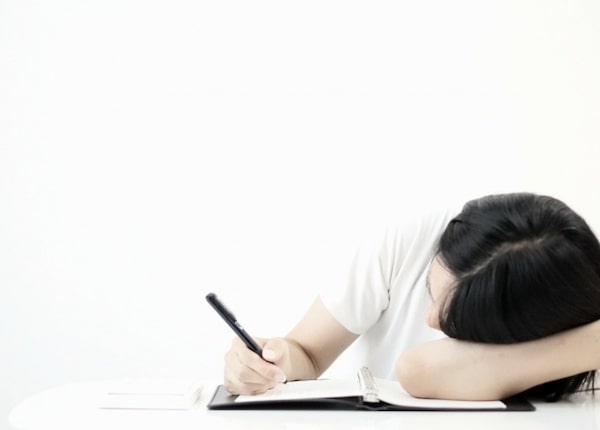
私の生活習慣に睡眠の質が下がってしまう原因があるのかを考えました。
睡眠の質が低下する原因
一般的に言われる睡眠の質が低下する原因には以下のようなものがあります。
- ストレス
- 運動不足
- 食生活の乱れ
- アルコールやカフェインなどの刺激物の摂取
- 不規則な生活リズム
- 環境の変化(例えば、旅行や引っ越し)
- 疾患や薬物の副作用
- 睡眠時無呼吸症候群
全てが完璧とは言い難いですが、私の場合に大きく影響するような原因が見当たりません。睡眠時間は一般的に適切と言われる7時間と必要十分。入眠する時にも、スマホを使うこともなく脳は緊張状態ではなくリラックスしているはずです。
睡眠の質を上げたいと思っていても自分ではどうにもならないような気がして、どうしたらいいのかをネットで調べると、睡眠の質を上げるには成長ホルモンがキーになるということを知りました。
成長ホルモンとは、身体の成長や修復に必要なホルモンで、主に深い眠りの間に分泌されます。成長ホルモンが不足すると、身体や精神の疲労が回復しなかったり、免疫力や肌のハリが低下したりします。
成長ホルモンを分泌させるには

一般的に22時前に寝ることや、ストレスを減らすことなどが効果的だと言われています。しかし、現代社会ではなかなか22時前に寝ることは難しいですし、ストレスも避けられません。
そこで私が試してみたのが、ドクターズチョイスのアルギニンサプリです。このサプリは、ノーベル賞を受賞しているイグナロ博士というアルギニンの第一人者が推奨する成分を忠実に再現しています。
アルギニンは、成長ホルモンの分泌を促進するアミノ酸で、3,600mg以上摂取することで効果があると言われています。また、ドクターズチョイスのアルギニンには、シトルリンや葉酸などの抗酸化成分も配合されており、血流や免疫力も向上させます。
最初は半信半疑でしたが、飲み始めてから1週間ほどで効果を実感しました。夜中に目が覚める回数が減り、朝起きたときにスッキリ感じるようになりました。昼間も眠気がなくなり、仕事や家事に集中できるようになりました。確実に肌もつやつやしてきています。
ドクターズチョイスのアルギニンサプリは品質世界ナンバーワンを追求しているメーカーが作っています。イグナロ博士の推奨成分を再現するだけでなく、安全性や吸収性も高いものが選ばれています。
返品保証があるのでリスクなし
このメーカーには、返品保証があります。少しでも商品に不満があれば、購入後90日以内なら返金対応してくれます。
また、他メーカーで品質の良い商品を見つけ、乗り換えたい場合も返品を受付けてくれます。ただし、乗り換えたいメーカーの商品情報や成分、なぜそちらの方が良いと思ったのかの意見を説明する必要があります。
金銭的なリスクは一切ありません。まず、このメーカーのものを試し朝の目覚めが期待ほど良くならなければ返品するでOKです。
そしてその後にまたどこかのメーカーを試してみるのはアリではないでしょうか。
90日保証の動画
アマゾンでも販売していますが価格は高いです。ですが、レビューはとても参考になると思います。
多くの人がスッキリ目覚めることができたなど高評価です。
